| かゆうイマリ様 『Blind blood』 |
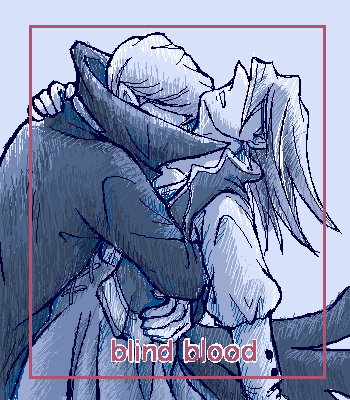 |
| ≪BACK||TOP||NEXT≫ |
|
Blind blood
蒼い月明かりの下、漆黒のマントに身を包んだ独りの男が呟いた。 冴え渡った夜の気配に染み込むようにひっそりとした口調だが、存在感のある重い言葉だった。 「いずれ血が体内を満たしお前は俺と同じく永遠の時を刻むだろう。完全なる闇の眷属としてもう二度と光のもとに立てなくてもか」 その言葉は青年の心に深く染込んでいく。 何と答えるか、青年には決まっていた。 ずっと、彼と出会ってから、その言葉を切り出してくれるのを待っていた。この世に未練はない。 独りで生きて来た自分にとって、彼の存在が全てであった。彼を孤独にしない為なら、陽の光など欲しくはない。月の光りだけで、彼の顔を見られる明かりがあれば充分すぎるほどだ。 彼と共に生きられるなら、惜しいものはなにもない。 「共に生きる術が一つしか無いなら迷わずそれを選ぶさ。……大丈夫オレは死にはしないよ。」 貴方は決して孤独ではもうないのだと言いたかった。 愛した人達を、そして友達を見送って来た彼の寂しい気持ちが青年の心を締め付ける。だから誰も愛しては、好きなっては、どのような形であってもそれはいけないことだと戒めて生きて来た彼の苦悩に満ちた長き時を消すことは出来なくとも、思い出に転化してあげたいと。 一時の気の迷いでもないし、現状を逃れたいからでもない。 陳腐な言葉を使えば、愛しているから、彼と共に生きて行きたい。 その傍らで、寂しげに笑う彼を抱き締めてあげたい。 それが今の自分の望みの全てだ。 自らにシャツの襟元を寛げて、月光の元に首筋を晒した。 青い血管が僅かに浮き出ているのが、孤独な男の視覚を捕らえる。 誘われるように男の白い牙が突き立てられた。 男は縋るようにその痩躯を抱き締めると、泣き笑いの表情のまま血の契約を実行する。 連れて行きたい気持ちと自分は彼を愛してしまう前に、ここを去らなくてはならなかったのにも関わらずそれが出来なかった自分のふがいなさと甘さの間で心が揺れていた。 でも、青年の腕は彼の背中に回されて、その顔には穏やかな笑みが浮かんでいた。 欲しかった全てを手に入れられる。 そんな笑みであった。 自分の迷いを振り払うように男は更に深く牙を突き立てた。 月だけが知っている血の契約を交わす儀式は始まったばかりであった。 |