|
セルロイドの月の下
「見ろよ。すっげぇな」 ジェットはまるで重力など感じられないような軽い足取りで窓辺まで歩み寄ると、デスクの上に両手一杯に抱えていたお菓子を置いた。 「ああ、凄いな」 と、ジェットが問い掛けた相手は、ジェットの背後にある大きな月を眺めていた。 暗い窓にぽかりと浮かぶ二十六夜月だ。ほっそりとした弓の形のようなフォルムであるが、その輝きは満月に匹敵するものがあった。今夜はハロウィンだから、月も浮かれているのかとらしからぬことを考えて、月の光を背に受けて浮かび上がる青年のしなやかなボディラインに更に目を細めた。 ギルモア博士からハロウィンの招待状を貰った。 戦いの日々だけではなく、ただ世界各地に散らばった仲間がこんなことで集まるのも悪くはないだろうとのことだった。ジョーにこっそりと聞いたところによると、ギルモア博士は子供の頃大きくなったら、お金持ちになって沢山のお菓子を子供に配りたいとそんなことを思っていたことがあると言っていた。科学者としての冷徹な一面と子供のような無邪気な一面が、アイザック・ギルモアと言う人物の構成するパズルの断片である。 日本に在住していて、ギルモア博士の親しい友人でもあるコズミ博士を招いてのパーティは、それは楽しく、騒がしく。フランソワーズとジョーの用意した仮装に身を包んで全員が子供のようにはしゃぎ、そして食べ、飲み、笑った。 最後に博士は少し酔ったのか赤い鼻を膨らませながら、小柄な自分の躯が隠れてしまうほどの大きな籠に入ったお菓子を嬉しそうに00ナンバー全員に配ったのだ。 ジェットは大はしゃぎで、魔女のコスチュームのスカートを捲り上げてそれを受け皿にすると抱えきれないほどの菓子を入れてもらっていた。 菓子を貰った者から部屋に戻り、パーティは日付が変わった頃にお開きとなったのだ。 「こんなに、沢山くれるなんて…」 可愛らしくラッピングされたお菓子の一つ、一つを月の明かりに翳して無邪気にどれから食べようかなと、呟く恋人に吸血鬼の仮装をした男は音もなく近付いていった。 「菓子は、明日でも腐らないだろう」 そんな彼の背後から耳元でそう囁くと、彼はピンクのセルロイドに包まれたマシュマロの袋を持ったまま振り向いた。そして、その袋と恋人の顔を見比べた後、徐にマシュマロの入ったピンクの袋を机に置くと、跳ねるように男から距離を置いて月が見える窓に背を向け笑う。 フランソワーズに戯れで塗られた赤いルージュの口唇の端がキュと上がる。 月明かりしかないのに、何故かそれがはっきりと見える。そのくせ、青い瞳は長い髪に隠れて表情は見えないが故に、その口唇が蠱惑的に男の目には映った。 「魔女の血って美味いの?」 と吸血鬼の仮装をしている恋人に問い掛ける。 「ああ、きっと、美味いだろうな」 誘われるようにその赤い口唇に血の気の失せた青い口唇を重ねた。 魔女の仮装をした彼からはルージュの匂いが、そして吸血鬼の仮装をした彼からは白粉の匂いがした。魔女と吸血鬼は月の光を浴びながら口付けを交わす。 黒っぽい衣装が混じりあい二人の間にある空間を埋めてしまうように、二人の影は長い時間重なっていた。 「甘いな」 吸血鬼がそう囁くと魔女は彼の口唇に指を這わせた。 「移っちまった」 ルージュが彼の口唇に移ってしまっていた。それ程に激しい口付けだったのかと思うと、躯が火照ってくる。最初に吸血鬼の仮装をした彼を見た時、心臓が高鳴った。がっしりとした厚い肩に乗ったマントが大きな歩幅で歩く彼につられてユラユラと揺れる様や邪魔とでも言うように跳ね上げる姿に見惚れた。 役者のブリテンが施した化粧もまた彼の怜悧な美貌を際立たせて、視線のやり場に困ったことなどいくつもあったのだ。でも、皆の居る前で恥ずかしくて、それを誤魔化すようについはしゃぎすぎてしまったくらいであった。 まるで、ジェットの指を追いかけるようにアルベルトの舌が口唇を撫でる。その淫らな舌の動きにジェットは思わず、唾を飲み込んでしまっていた。 「なあ、吸わせてくれよ」 ベッドモード全開で耳元に囁きを吹き込むアルベルトにジェットは逆らえるはずもない。 「オレの血なんか美味くねぇよ。吸血鬼さん。それに、吸血鬼は美女がお好きだろう」 と、にいっと歯を剥いて笑ってやると、格好良いハンサムな吸血鬼は可愛らしい魔女にこう囁いたのだ。 「俺は趣味が悪くってな。跳ねッかえりのカワイコちゃんが好みなんだ」 「誰がっ!!カワイコちゃんだっつうの。それにサイボーグの血は美味くねぇぜ、きっと…」 今度は舌を出して、アンカベーをしてやる。 くくっと喉の奥であまりにも跳ねっかえりの魔女いや、魔女っ子らしい彼の動作に小さな笑いが零れる。その可愛らしい反応にいとしさを覚えずにはいられない。 「ものの本によるとな。血じゃなくって精気を吸い取る吸血鬼もいるんだそうだ」 背中から、腰を経て魔女のコスチュームの上から少し硬くなりつつある彼のペニスを撫でると、僅かに甘い吐息が頬に掛かる。 「で、オレは吸血鬼に襲われて、精気吸い取られちゃうわけ?」 「そう言う事」 「じゃぁさ」 ジェットはアルベルトの肩に手を置いて、誘うように抱きこむと今度は甘えた声でアルベルト耳元に囁きを吹き入れる。 「優しくしてくれよ。吸血鬼さんに精気吸い取られちまってもいいからさ」 ちょっとだけ遠まわしの、激しいセックスへのお誘いに吸血鬼はその仮装に相応しい深い笑みを零すが、抱き合っているジェットには見えなかった。獲物を見つけた猛獣が舌舐めずりするような、とでも表現すればよいのかと思うような笑みであった。 「ああ、一滴も残らないぐらいにな……」 アルベルトはそう囁くと、ペニスを撫でたその手をスカートの下から忍び込ませる。最初はスパッツを履いていたのだが、はしゃぎすぎてビールで濡らしてしまった彼は今は下着以外はスカートの下には身に着けてはいなかった。 滑らかな白い皮膚の感触を味わう。 白い絹の手袋の感触にジェットは足を戦慄かせた。鋼鉄とも人工皮膚の手袋とも違うその感触にもどかしさを感じる。 太股辺りから下着のラインに沿って何度も撫でられ肝心のその場所を愛撫されないもどかしが堪らなくて、自分を抱き締める分厚い男の胸に縋り付くように手を回した、生身ではない硬い感触がジェットを安心させる。 ここに居れば大丈夫だと言う絶対的な信頼が、其処にはあった。 決して、彼は自分を人形のようには扱わない。どんなに惨いと思える行為だとしてもその向こうには愛情だけが存在している。愛しいと思うが故の行為だとジェットには分かるから、彼の齎す感覚の全てを享受できてしまうのだ。 「っあん」 もどかしくて、もっと触れてもらいたくて腰を彼の固くなりつつあるペニスに自らのを押し付けた。自分の僅かな感じているのだというシグナルに反応してくれる彼のペニスがいとしくてならない。早く、惨く貫かれて彼以外の全てを忘れ去ってしまいたいと、鼻を男の太い首筋に甘えるように擦り付けてみる。 いつも使っているコロンと整髪料の他に、白粉や酒、煙草の香りがしてくる。 そして、パーティの最後の方でコズミ博士の提案で楽しんだゲームでフランソワーズを抱きかかえて走ったせいなのか僅かに彼女が今日つけていた甘い香水の香りが残っていた。 他の女の香水だったら、許してやらないけどと、ジェットは快楽に侵食されつつある頭の片隅でそう考えていた。でも、明日の朝にはオレの匂いで一杯にしてやるんだと、ジェットはついライバルにもならないフランソワーズの残した甘い香りに奇妙な対抗心を持ってみせたりしていた。 その間にアルベルトのいつもとは感触の違う手はジェットの下着に掛かっていた、勃ち上がったペニスに辛うじて引っかかっているだけの下着から手を差し入れて、はみ出した恥毛の感触を味わうように何度も撫でられる。 「いゃ…。じらすなって」 目元を赤く染めて、男の頬に舌を這わせる。耳の中まで舌を伸ばして、ねちっこく舐めまわしてやると男はくすぐったいと肩を竦めておざなりの反抗をしてみせる。ピチャピチャという舌の動く音が直接鼓膜に響き、つい抑えようとしていた気持ちに火が点いてしまった。 「ったく、後悔するなよ」 と囁くと返事も聞かずに、アルベルトはしゃがみ込んで、ジェットのスカートの中に顔を突っ込んでしまった。 「ッっちょ……、オイッ!!」 そのままベッドに連れて行ってもらえると思っていたジェットの抗議の声が上がる。スカートの中に潜り込んだアルベルトは下着を下ろすと、其処からピンと勢い良く飛び出して来たジェットのペニスをぱっくりと咥えてしまったのだ。 「っあん」 逃げ腰になるジェットを逃がさないとばかりに、小さな尻を衣装の上から痛い程に握るとぐいっと自分の方に引き寄せる。自分を支えていた窓ガラスが遠くなりジェットの上半身は揺らいだ。 この僅かな距離がアルベルトを頼らざる得ない状況を作り上げてしまった。 こうなっては自分で立っていられなくなるのは時間の問題だ。せめて、窓ガラスが背に当たっていれば良いのだが、アルベルトはそれすらも許さないと腰を自分に引き寄せてしまった。 ジェットはスカートの中に潜り込んだ男の頭を布の上から必死で掴んだ。 「いゃっ、………っぁぁあん」 鼻に掛かった甘い声が室内を満たしていき、月に照らされた痩躯が戦慄き魔女が悶えるシルエットが窓に浮かび上がった。その姿をもっとよく見たいと月が言うようにその光は益々明るくなっていく。 布の向こうで、ジェットの鼻に掛かった喘ぎが聞こえてくる。 逃がすまいと捕らえた尻のせいで、窓を支えに出来なくなっていることは分かっている。必死でその躯を支えようと不埒な行為をしている男の頭に縋ってくるのも、もう計算済みであった。 自分をどんなに潤んだ瞳で見詰めて誘っていたかなんて、知っている。濡れたとわざわざ男の目の前でスパッツを脱いで見せたり、暑いとスカートを捲り上げたり、そんな姿を見てそのまま放置してやれるほどに、紳士ではないと知っていてこの魔女っ子は誘ったのだ。 いつもだ。 分かっていて誘う。惨くされて、声が枯れる程に抱かれると分かっていて自分にその身を投げ出してくるどころか、自分から誘って来るのだ。 それに簡単に乗る自分も自分なのだが、誘われなくとも頭の中はジェットのことで一杯なのだ。どうやって、抱いてやろう。どうやって啼かせてやろうとそんなことを飽きもせずに考えている。 こんなに美味しいハロウィンの夜を逃す馬鹿者はいるものかとアルベルトはジェットの震えるペニスにブリテンが嵌めてくれた義歯を軽く立ててみた。ぴくんとジェットのペニスが震えた。まるで、もっとというように、ぬめる液体がアルベルトの喉を潤していく。 そんな可愛らしいペニスを咥え、掴んだ双丘をぐっと左右に開くと緊張するように尻の筋肉がきゅっと締まった。無理に後孔を広げられる感触にジェットが感じているのだ。 その証拠に頭上からは、喘ぎが更に細かなリズムを刻み出している。 義歯をわざと震えるペニスに立てると、その声は大きくなった。 「イタッ……。っうん」 でも、嫌だとは言ってはいない。この痛みにジェットは感じているのだ。 アルベルトは今夜は吸血鬼だからなと、笑ってその義歯をジェットの硬くなったペニスに突き立てた。 「っいゃ……、イッ、っあああんぁあぁぁああんっ!」 それが快楽なのだと、そう告げるようにジェットは達してしまっていた。アルベルトはそれを零さすように飲み干すと、味の濃さににんまりと笑う。前にセックスをしたのは2週間前だ。会わない間、ジェットは自分ですらあまり慰めていないのだということが知れて、男の独占欲を満足させてくれる。 「バカッ…、ヤロウっ!」 掴まれていた頭がぽかりと叩かれた。 へへへと笑って顔を出すと、頬を染めて目を潤ませた可愛らしい彼だけの魔女が其処にいた。 「痛いじゃないか、馬鹿、エロ吸血鬼っ!」 「でも、感じただろう」 間違いがない。歯を立てた瞬間に逐情してしまったのだから、言い逃れは出来ない。そんな状況だといつも、拗ねてみせたりするのだが、その拗ね方が保護欲の旺盛な男には可愛らしく見えてしまう。割れ鍋になんとやらのカップルなのだ。 「でも、イタイ、イタイ、イタイ……」 立ち上がって何度もイタイと連呼する、魔女っ子の赤味を帯びた金髪を宥めるように撫でてやる。 「じゃぁ、どうしたら痛くなくなるんだ」 と視線を合わせたアルベルトの少しだけ困惑した表情を見て満足したのか、ジェットはアルベルトに全てを預けるように抱きついてきた。 「だったら、痛くなくなるまで、撫でてくれよ」 「分かった、ついでに舐めてやる」 そう返した男を引き剥がしてジェットはその顔をマジマジと見詰めた。そして、綺麗に笑うとうんとそう頷いたのだった。 「やっぱ、あんたエロ吸血鬼だな。でも、ハロウィンナイトだから、許してやるっ!」 と笑いながら再び、アルベルトに抱きついた。 そんな二人を二十六夜の月は優しく、温かく見守るように輝いていた。一晩中、その月に照らされながら、魔女と吸血鬼は種族を超えた愛を確かめ合ったのである。 |
| 高城キリ様 |
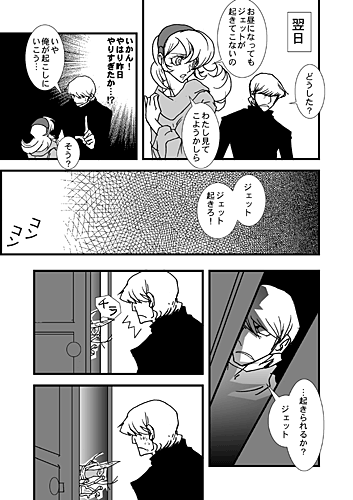 |
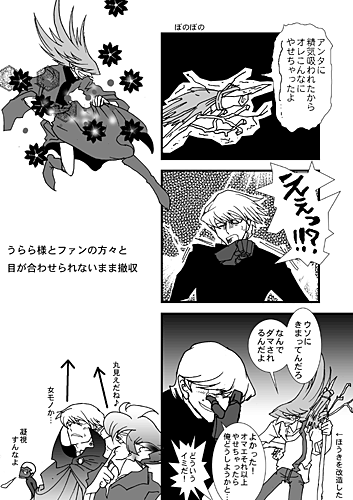 |
| ≪BACK||TOP||NEXT≫ |